「内申点が大事っていうけど、親にできることって何?」中学生の進路を考えるとき、避けて通れないのが“内申点”。でも、成績は本人の努力次第とはいえ、親としても何かできることがあるなら…と考えますよね。
この記事では、親として「やりすぎず・でも見守る」ためのヒントをまとめました。私自身の反省や体験談も交えながらご紹介します。
内申点とは?まずは親がしくみを理解しておこう
内申点とは、定期テストの点数だけでなく、授業態度・提出物・日々の取り組みなどを含めた「学校生活の総合的な評価」です。都道府県によって計算方法に違いがありますが、受験の際に内申点が大きく影響するのは全国共通。
まずは、保護者自身が「どの科目がどんな配点で評価されるのか」「通知表のどの部分が内申点に関わるのか」を知っておくことで、子どもとの会話にも説得力が生まれます。
ガミガミ言うより、「応援モード」で関わるほうがうまくいく
「ちゃんとやってるの?」「提出物出したの?」「そんな点じゃダメでしょ!」つい言いたくなりますが、言えば言うほど子どもは心を閉ざしてしまいがちです。
私も経験ありますが、厳しく言ったからといって改善されるわけではなく、逆に「うるさいな」と反発されたことも。
それより、「今日もお疲れさま」「何か手伝えることある?」と応援スタンスで関わると、子どものやる気に火がつくことが多いです。
提出物や持ち物は“声かけだけ”で見守る
提出物の出し忘れやプリントの紛失は、内申点に意外と影響します。ただし、親がすべて管理してしまうと子どもの「自己管理力」が育ちません。
「プリント配られてた?」など、さりげなく聞いてみるくらいがちょうどいい距離感。必要なら「ToDoリスト」や「提出物チェック表」などを一緒に作るのもおすすめです。サポートはするけれど、最後の確認は子ども自身に任せるスタンスがベスト。
定期テストの勉強は「環境づくり」と「声かけ」で支える
テスト勉強を「やりなさい!」と叱るよりも、集中しやすい環境を整えてあげることの方が効果的です。静かなスペースを用意する、スマホの置き場所を相談する、一緒にタイムスケジュールを立ててみる——そんな小さなサポートが、意外と効きます。
また、無理に口を出すより、「頑張ってるね」「応援してるよ」のひと言が、思春期の子どもの背中を押してくれることも多いです。
生活面の安定が、学習態度や内申点にもつながる
遅寝・朝寝坊・朝ごはん抜きなど、生活リズムの乱れは、授業中の集中力や提出物の遅れにもつながります。内申点を上げたいなら、まずは生活習慣を整えることが土台になります。
「早く寝なさい!」と怒るより、「一緒に明日の準備しようか」「明日は朝ごはん、好きなの作ろうか」など、さりげなく整えていくのが親の腕の見せどころかもしれません。
この記事のまとめ
内申点アップのために、親がやれることは意外とたくさんあります。でもそれは、「子どもをコントロールする」ことではなく、「見守りながら支える」こと。大事なのは、子どもが「自分でやろう」と思えるような関わり方です。
完璧じゃなくてOK。子どもも親も、少しずつ“成長のペース”をつかんでいければ、それが一番の力になるはずです。
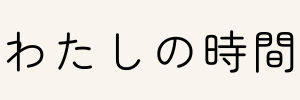
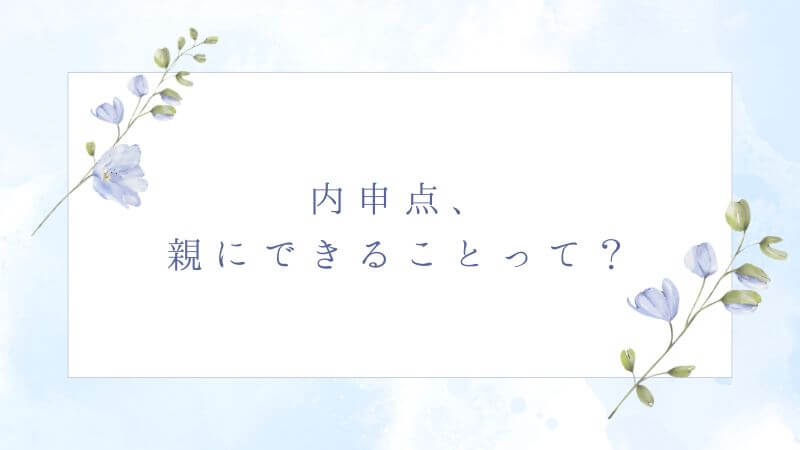
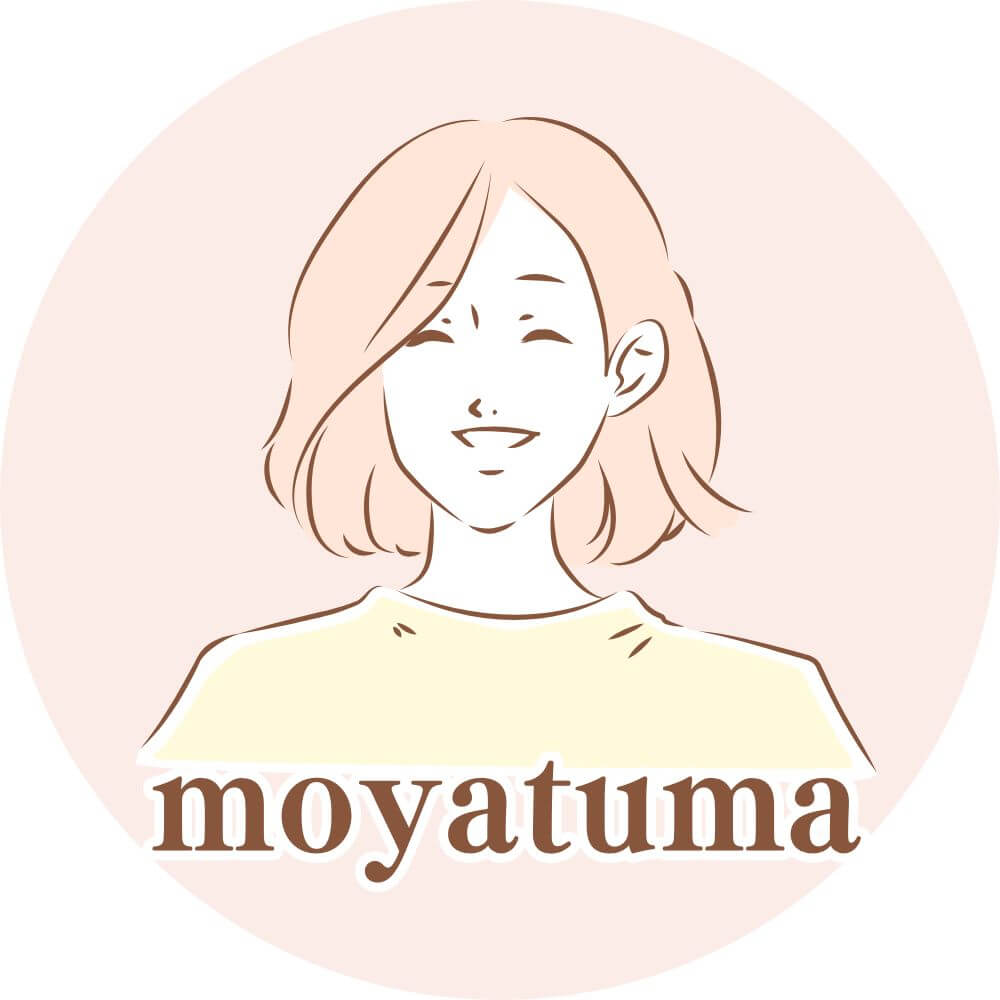
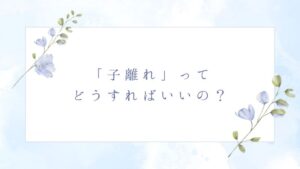


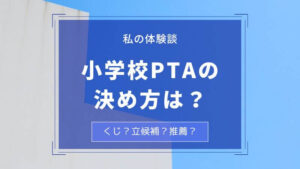
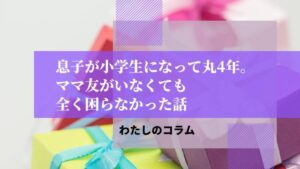
コメント